システム構築予算の見積もり方法:ボトムアップ法を徹底解説
システム構築の予算を見積もる際、どのような手法を用いるかはプロジェクト成功の鍵を握ります。見積もり手法にはさまざまな種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。今回はその中でも「ボトムアップ法」と呼ばれる手法に焦点を当て、システム構築の予算見積もりに役立つステップを詳しく解説します。
ボトムアップ法は、新規システム開発にも適用可能な手法で、精緻な見積もりが可能です。今回はこの手法を使った予算見積もりの基本的な流れを紹介します。全体で7つのステップに分かれていますので、それぞれの工程について理解を深めていきましょう。
1. 難易度別工数テーブルの作成
まず最初に、「難易度別工数テーブル」を作成します。システム構築に必要な機能ごとに、難易度をA、B、Cの3段階にランク分けし、それぞれに対して予想される工数を設定します。例えば、単純な参照画面は「C」、更新画面は「B」、複雑な一覧更新画面は「A」といった具合です。
これらのランクに対して、要件定義から総合テスト完了までに必要な工数を、おおよその人数月で見積もります。もし標準的な枠組みでカバーできない機能がある場合は、個別に工数を見積もり、Sランクとして扱います。
2. 機能一覧(難易度付き)の作成
次に、システムの機能一覧を作成します。この際、各機能に対して事前に決めた難易度ランクを付けていきます。画面やバッチ、インターフェースなど、システムの全機能を網羅することが重要です。
これにより、どの機能がどれほどの開発負担を伴うのかが明確になります。難易度別工数テーブルに基づき、各機能の開発負担を具体的に数値化しましょう。
3. 機能一覧(難易度付き)に基づく総工数の算出
機能一覧が完成したら、難易度別工数テーブルを使って、各機能にかかる工数を計算します。ここでは、簡単に言えば「機能数 × 各機能の工数」を計算するだけです。この時点で、システム開発に必要な最小限の工数が見えてきます。
4. 総工数をフェーズ別に按分
次に、算出した総工数を開発フェーズに按分します。要件定義、設計、開発、テストといった各フェーズにおける工数の割合を算出し、各フェーズの工数を割り当てます。ネットで検索すれば、一般的なフェーズ別の工数割合が見つかるので、それを参考にして工数を割り振りましょう。
また、各フェーズにどのようなメンバー(プロジェクトマネージャー、チームリーダー、開発者)を配置するかも決定します。この段階では、工数が小数点になることもありますが、その場合は切り上げを行って要員数を決定します。
5. インフラ・アーキテクチャ関連の工数の見積もり
インフラやアーキテクチャに関する工数は、タスクごとに要員を配置して積み上げます。例えば、システムを動かすために必要なインフラ設計や共通コンポーネント開発のための工数を、タスク単位で見積もります。
これらはアプリケーションの開発とは別に、重要な要素として取り扱う必要があります。インフラ担当者を数ヶ月にわたって配置する場合、どの時期にどのような作業を行うかを明確にし、その工数を積み上げていきます。
6. 管理工数、レビュー工数、会議工数の積算
プロジェクトの全体工期が決まったら、管理工数やレビュー工数、会議工数を追加します。これらの工数は、特にリーダー層のメンバーが担当する作業です。プロジェクト全体の管理や進捗確認、品質チェックのための工数をしっかりと積み込むことが重要です。
7. バッファの設定
最後に、予期しない問題や遅延に備えて、バッファ(余裕工数)を設定します。これにより、予算や納期が守れないリスクを減らし、プロジェクトをスムーズに進行させることができます。バッファの量は、プロジェクトの規模や複雑さに応じて適切に調整しましょう。
まとめ
システム構築の予算見積もりを行う際、ボトムアップ法は非常に有効な手法です。細かいステップを踏んで、機能ごとの工数を積み上げていくことで、実際の開発にかかる工数や必要なリソースを正確に把握できます。この方法をマスターすれば、より信頼性の高い予算見積もりを行い、プロジェクトを成功に導くことができるでしょう。
今後、システム構築予算の見積もりを行う際には、ぜひボトムアップ法を取り入れて、効率的な予算策定を行ってください。

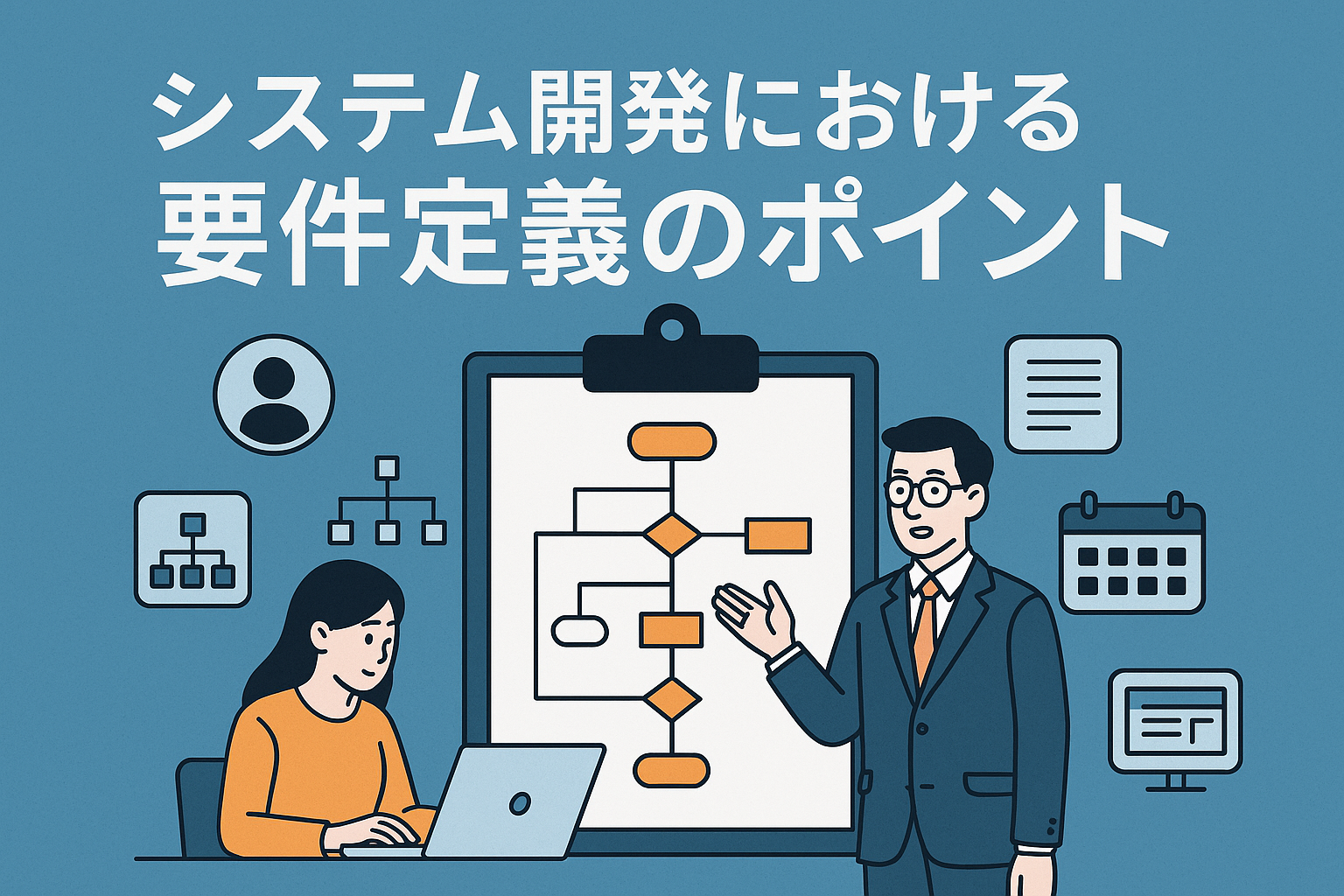
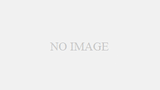
コメント